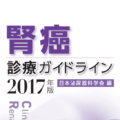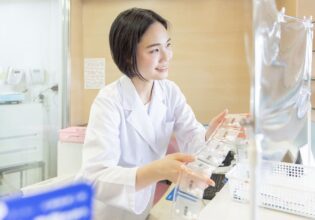抗がん剤の副作用は、治療直後にあらわれるアレルギー反応など100種類ほどの現象があります。例えば、吐き気や食欲低下、脱毛など、症状が出る時期がある程度決まっています。
なぜそういった副作用が起こるのでしょうか。その理由は、抗ガン剤が消化管粘膜や嘔吐を引き起こす脳の一部を刺激するからです。
また、飲み薬の抗がん剤治療のみの患者さんを対象にした薬剤師外来を設置しているところもあります。
本記事では、抗がん剤の副作用について解説します。
Contents
1. 抗がん剤の副作用のメカニズムについて

抗がん剤の副作用は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を与えるために起こります。副作用のメカニズムは、抗がん剤の種類や投与方法によって異なりますが、大きく以下の3つに分けられます。
1-1. 細胞分裂への影響
抗がん剤の多くは、細胞分裂の過程を阻害することでがん細胞の増殖を抑えます。しかし正常な細胞も分裂しているため、抗がん剤の影響を受けてしまいます。特に骨髄や消化管粘膜、毛根など、細胞分裂が活発な組織は影響を受けやすい傾向があります。また骨髄抑制(白血球減少、赤血球減少、血小板減少)や消化器症状(吐き気、嘔吐、下痢、口内炎)、脱毛などの副作用が現れます。
1-2. DNAへの影響
一部の抗がん剤は、がん細胞のDNAに直接作用し、DNAの複製や修復を阻害することがります。この作用は、正常な細胞のDNAにも影響を与える可能性があり、二次がんのリスクを高めることがあります。
1-3. 特定の細胞や臓器への影響
一部の抗がん剤は、特定の細胞や臓器に特異的に作用し、副作用を引き起こします。例えば心臓に影響を与える抗がん剤では、心筋障害や不整脈が起こることがあります。また腎臓に影響を与える抗がん剤では、腎機能障害が起こることがあります。
1-4. 代表的な副作用のメカニズム
1-4-1. 骨髄抑制
抗がん剤が骨髄の造血幹細胞に影響を与え、白血球や赤血球、血小板の産生を抑制します。また白血球減少により感染症のリスクが上昇し、赤血球減少により貧血が起こり、血小板減少により出血しやすくなります。
1-4-2. 消化器症状
抗がん剤が消化管粘膜の細胞に影響を与え、粘膜の炎症や損傷を引き起こします。また一部の抗がん剤は、脳の嘔吐中枢を刺激し、吐き気や嘔吐を引き起こします。
1-4-3. 脱毛
抗がん剤が毛根の細胞に影響を与え、毛髪の成長を阻害します。ただし脱毛は一時的なもので、治療終了後に回復することがほとんどです。
1-5. 副作用の対策について
副作用を軽減する対策には、抗がん剤の投与量や投与スケジュールの調整があります。また支持療法(吐き気止め、制吐剤、感染症対策など)も行います。
2. 抗がん剤の副作用出にくい人特徴について
抗がん剤の副作用は、個人差が大きいのが特徴です。そのため同じ抗がん剤を使用しても、副作用の程度や種類は人によって異なります。副作用が出にくい人の特徴として、以下の点が考えられます。
2-1. 体質や遺伝的要因
2-1-1. 遺伝子
抗がん剤の代謝や排出に関わる遺伝子の違いにより、副作用の出やすさに個人差が生じます。例えば特定の遺伝子変異を持つ人は、副作用が出にくい、または出やすいといった特徴があります。近年では、遺伝子検査で個々の患者さんに最適な治療法を選択することが可能になってきています。
2-1-2. 免疫力
免疫力が高い人は、抗がん剤による正常細胞へのダメージからの回復が早く、副作用が出にくい傾向があります。例えば健康的な生活習慣を送っている人は、免疫力が高い状態を維持しやすく、副作用のリスクを低減できる可能性があります。
2-1-3. アレルギー体質
アレルギー体質の人は、抗がん剤に対する過敏反応を起こしやすく、副作用が出やすい傾向があります。また過去に重篤な副作用の経験がある人も、同様に注意が必要です。
2-2. 体の状態について
2-2-1. 若い人は副作用が出にくい
一般的に、若い人は高齢者に比べて体力があります。そのため副作用からの回復も早いため、副作用が出にくい傾向があります。
2-2-2. 基礎疾患がある人は副作用が出やすい
糖尿病や腎臓病、肝臓病などの基礎疾患を持つ人は、抗がん剤の副作用が出やすい傾向があります。そのため基礎疾患の状態によっては、抗がん剤の投与量や投与スケジュールを調整する必要があります。
2-3. 精神的要因について
2-3-1. 精神状態の影響
精神的に安定している人は、ストレスによる免疫力低下を防ぎ、副作用が出にくい傾向があります。逆に不安や恐怖心が強い人は、自律神経の乱れから、吐き気や嘔吐などの副作用が強く現れることがあります。
3. 時間の経過別の抗がん剤の副作用
3-1. 投与後数日間~一週目
3-1-1. 自覚症状でわかる副作用
抗がん剤を投与した後の数日間で、自覚症状でわかる副作用としては、「吐き気」「アレルギー」「血圧低下」「不整脈」「呼吸困難」などがあります。またその後には、「吐き気」「食欲低下」「全身倦怠感」「便秘」「下痢」「味覚障害」もあります。
3-1-2. 血液検査でわかる副作用
投与後一週間目で血液検査でわかる副作用には、「肝機能障害」や「腎機能障害」があります。
3-2. 投与後2週目
3-2-1. 自覚症状でわかる副作用
抗がん剤投与後の二週目で、自覚症状でわかる副作用としては、「口内炎」「下痢」「全身倦怠感」「だるさ」があります。
3-2-2. 血液検査でわかる副作用
投与後二週間目でわかる副作用には、「骨髄抑制」「白血球好中球減少」「血小板減少」「リンパ球」「赤血球」「ヘモグロビン減少」などがあります。
抗がん剤の副作用の骨髄抑制とは
骨髄は、血液細胞(赤血球、白血球、血小板)を生成する組織です。抗がん剤はがん細胞だけでなく、骨髄の細胞にも影響を与えるため、血液細胞の生成が抑制されることがあります。これを骨髄抑制といいます。骨髄抑制によって起こる症状には、「白血球減少」「赤血球減少(貧血)」「血小板減少」などがあります。骨髄抑制のレベルは、使用する抗がん剤の種類や量、患者さんの状態によって異なります。
3-3. 投与後3週目~4週目
3-3-1. 自覚症状でわかる副作用
抗がん剤投与後の3週目~4週目で、自覚症状でわかる副作用としては、「脱毛」「頭痛」「神経毒性」「手指足しびれ」「かゆみ」があります。
3-3-2. 血液検査でわかる副作用
投与後3週目~4週目でわかる副作用には、「骨髄抑制貧血」があります。
4. 抗がん剤の副作用と対策について

抗がん剤の副作用には、死に至るリスクのあるものとないものの2種類があります。また抗がん剤はがん細胞を破壊するだけでなく、正常細胞も影響を受けます。そしての副作用の中には、身体的にも精神的にも苦痛を感じるものがあります。
4-1. 血液毒性
骨髄などの造血器における「造血障害」と、抹消における「血球の破戒」から誘発されます。造血障害は、抗がん剤が骨髄系幹細胞や造血前駆細胞に作用して分化増殖を抑制することで起こります。また血球破戒は、免疫学的機序で起こることが多く、「薬剤吸着型」と「免疫複合型」に分類されています。
白血球減少の場合、白血球が減少しても自覚症状はありません。ただ細菌が感染しやすい状態になっており、感染症の症状が起こる可能性があります。
また好中球減少は、白血球減少と似ていています。好中球減少自体に特有の症状はなく、多くは感染症にかかったときに発見されます。発熱し、口や肛門周辺に痛みを伴う潰瘍が発生することがあります。
血小板減少は、出血が起こりやすく、血が止まりにくくなります。また症状として青痣が出来やすくなったり、手足に点状出血が起こったりします。
4-2. 消化器毒性
抗がん剤の投与によって、高い確率で起こる非血液毒性の1つが、消化器毒性です。「吐き気」「嘔吐」「食欲不振」「便秘」「下痢」「口内炎」等を引き起こします。
抗がん剤治療では、口内炎を起こしやすい薬剤の投与を受けた時、口内炎が起こります。また放射線治療では、口の粘膜に放射線が直接当たる時に、口内炎が起こります。例えば、強い抗がん剤治療を受けると、粘膜が腫れ気味で赤くなります。そして表面は少しでこぼこになり、粘膜の一部が剝がれて潰瘍ができます。
4-3. 心毒性
心毒性は、心臓に悪影響を及ぼす毒性です。また心筋障害が悪化して、心不全を起こす可能性があります。例えば心筋障害の症状としては、「動悸」「息切れ」「呼吸困難」「身体のむくみ」「体重増加」があります。
心不全の場合、送り出される血液が不足し、体全身に色んな症状を引き起こします。特に多い症状として、「動悸」「息切れ」「呼吸困難」「むくみ」があります。
5. まとめ
抗がん剤の副作用は、約100種類ぐらいあります。治療直後に現れるものや、1~2週間後に出るもの、2週間以降に出るものなどがあります。
そういった現象が起こる理由は、抗ガン剤が消化管粘膜や嘔吐を引き起こす脳の一部を刺激するからです。
従来の抗がん剤は、天然物質や化学合成物質から作られています。
また近年は、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)による治療成績向上には目覚ましいものがあります。
本サイトでは、そういった最新情報どんどん発信していく予定です。