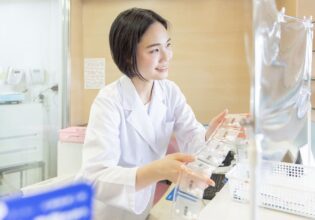在宅薬剤師は、患者さんが住み慣れた自宅や施設で安心して療養生活を送れるように、薬の専門家として多くの役割を担っています。超高齢化社会が進む日本においては、政府は地域包括ケアシステムを推進しています。その中で、在宅薬剤師は重要な役割を担っています。
主な役割は、「薬剤の調剤」「搬送」「服薬指導」「健康状態の管理」などがあります。また医師や看護師、ケアマネージャーと連携し、チームとして患者さんの健康をサポートします。在宅薬剤師という仕事は、患者さんの自宅というプライベートな空間に踏み込む側面があります。そのため、日頃のコミュニケーションを通じて、患者さんやその家族との信頼関係を築くことがとても重要です。
またいくつかの課題も存在します。まず第一に、在宅医療に対応できる薬剤師の不足です。特に地方ではこの傾向は顕著です。次に、業務量の多さと複雑さです。例えば「患者さん宅への訪問」「調剤」「書類作成」など多岐に渡り、残業につながる要因でもあります。本記事では、在宅薬剤師の現状や課題、解決策について詳しく解説します。
1. 在宅薬剤師の背景

1-1. 団塊の世代が全て75歳以上になる「2025年問題」
「2025年問題」は、団塊の世代が全て75歳以上の後期高齢者になることです。例えば、75歳以上の一人あたりの医療費は、74歳以下の方の3倍以上かかります。そのため、今後急激に医療費や介護費用が増加します。
また医療費だけでなく、病院のベット数の問題もあります。病院のベット数は年々減少していますが、現在1500万人の後期高齢者は2025年には2200万人まで増加する見込みです。つまり、医療現場がパンクする危険をはらんでいるのです。そういったリスクを回避する上でも、在宅医療は重要な施策になります。
1-2. 最後は自宅で迎えたい方が約55%に
厚生労働省が作成した平成28年度の全国在宅医療会議の資料では、約55%の方が自宅で最期を迎えたいと考えています。その次が病院です。自宅で最期を迎える大切なポイントは、病状に合わせた適切な在宅医療を受けれるかどうかです。そういった側面において、在宅患者へ最適な薬物療法の提供を行う在宅薬剤師の役割は重要です。また訪問看護ステーションや、ケアマネージャーなどの介護職との横の連携も大切です。
1-3. 在宅薬剤師の資格とは
在宅薬剤師には、「在宅療養支援認定薬剤師」資格の取得が推奨されています。この資格は、一般社団法人日本在宅薬学会による資格制度です。在宅療養支援認定薬剤師認定試験においては、5つの申請資格を満たし、必要書類を申請する必要があります。
2. 在宅薬剤師の仕事内容について

2-1. 患者さんの状態に合わせた調剤
処方箋に基づき、患者さんの状態に合わせた調剤を行います。具体的な内容を、以下に記します。
2-1-1. お薬の一包化
服用期間が同じ薬や、1回に複数の錠剤を服用する場合、まとめて1包にします。そうすることで、飲み間違いや錠剤の紛失を防ぐことができます。また手が不自由で、お薬を探したり取り出すのが困難な方に便利です。
2-1-2. お薬の懸濁法
錠剤・カプセルをそのままか亀裂を入れて、温湯(約55℃)に入れ、崩壊・懸濁させて投与する方法です。例えば錠剤・カプセルが飲みにくい患者さんでも、楽に服用できます。
2-1-3. 在宅医療用麻薬の投与・管理
医療用麻薬の主な効能や効果は、激しい疼痛時における鎮痛、鎮静、鎮痙です。その中でも、癌による疼痛のある患者さんは痛みを緩和することができます。ただし在宅医療では、医療従事者の観察が行き届きにくい状況での薬剤管理になります。休日に薬が不足しないようにしたり、小児やペットの手が届かない場所での保管が重要です。また未使用の麻薬の返却や他人への流用防止も、在宅医療用麻薬管理の大切なポイントです。
2-1-4. 無菌調剤
一定の無菌環境が保たれた無菌調剤室(クリーンルーム)で、高カロリー輸液や医療用オピオイド注射薬などの調剤します。白血病や再生不良性貧血、骨髄異形成症候群などの患者さんが対象になります。
2-2. 患者さんの自宅へ医薬品等を供給する
在宅医療を利用される患者さんは、通院が困難なことが予想されます。そういった患者さんに、薬剤師が医薬品や衛生材料を届けることは、在宅薬剤師のメインの仕事の一つです。
2-3. 薬の飲み合わせの確認・飲み忘れ防止
高齢者になると、複数の病気にかかることが多くなります。その結果服用薬の種類や数が多くなり、理解不足や飲み忘れが発生します。例えば飲み合わせ(相互作用)の場合、複数の薬の成分同士が反応し、予想外の強い作用が出たり、逆に薬が効きにくくなることがあります。 そういったことを防ぎ、適切な在宅医療を実施するためにも、在宅薬剤師の役割は大切です。
2-4. 服薬指導をする
2-4-1. 患者さんやご家族との信頼関係の構築
訪問の際は、まず自身の名前と所属を明確に伝え、訪問の目的を説明します。また患者さんやご家族の目を見て、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。また者さんの自宅は、プライベートな空間です。事前に訪問許可を得ているとはいえ、デリケートな情報に触れることもあるため、常にプライバシーに配慮した言動を心がけます。話し方については、患者さんの聴力や認知機能に合わせ、静かで落ち着いた場所を選び、ゆっくりと、はっきりと話すように心がけます。必要に応じて、文字や図を用いるなど、視覚的な情報も活用しましょう。
2-4-2. 患者さんの状況・生活背景の把握
嚥下機能、視力、聴力、認知機能、ADL(日常生活動作)などを総合的に評価し、服薬方法や指導内容を調整します。例えば錠剤やカプセルが飲みにくい場合は、口腔内崩壊錠、OD錠、液剤、散剤への変更を医師に提案したり、簡易懸濁法などの服用方法を指導したりします。また服薬カレンダー、お薬ボックス、一包化などを用いて、飲み忘れや誤薬を防止する工夫を提案します。
2-4-3. 生活習慣の把握
食事の摂取状況、睡眠時間、排泄状況、飲酒・喫煙習慣、運動量などを把握し、薬の効果や副作用への影響を考慮します。例えば食直前に服用する薬の場合、患者さんの食事時間に合わせて服薬を促すなどの具体的なアドバイスができます。
2-4-5. 生活環境の確認
薬の保管場所、保管方法、衛生状態などを確認します。直射日光が当たる場所や湿気の多い場所を避け、適切な温度で保管できるよう助言します。
2-4-6. 介護・介助状況の把握
誰が薬の管理をしているのか、服薬の介助は誰が行っているのかなど、家族や介護者の関与状況を把握し、必要に応じて介護者にも指導を行います。特に、麻薬などの管理が必要な薬剤の場合、慎重な確認と指導が求められます。
2-5. 副作用等のモニタリング
薬剤師による副作用モニタリングは、QOL(生活の質)低下の防止や処方カスケードの回避、減薬に貢献できます。そのためには、網羅的な症状のヒアリングや聞いた症状が薬の効果なのかの確認、その症状への対応が必要になります。
2-6. 医療福祉関係者との連携と情報共有
在宅薬剤師が患者さんの治療に関して、ケアマネージャーなどの介護職と連携することがあります。その場合、薬剤師からは「服薬介助」「スケジュールの調整」「介護職が訪問した時の体調チェック」などの依頼をします。また薬剤師の「訪問指導内容」を共有したり、「入院時の服薬情報」を提供します。
3. 在宅医療における薬剤に関するリスクとは

3-1. 加齢による合併症とそれに伴う多剤併用傾向について
まず加齢に伴って、人は体に生理的な変化が生じることを理解する必要があります。例えば腎臓や肝臓、心臓などの主要な臓器の機能が徐々に低下します。これは、薬物療法における薬剤の代謝や排泄に影響を与えます。また高齢になると、免疫機能が低下します。その結果、感染症にかかりやすくなったり、治りにくくなります。それら以外にも、骨粗鬆症のリスクや身体能力の低下や転倒のリスクが増加します。
それらの生理的変化を背景に、高齢者に見られる合併症には循環器疾患では高血圧症や脂質異常症、糖尿病や心不全などがあります。また脳血管疾患では脳卒中があり、呼吸器疾患では慢性閉塞性肺疾患や肺炎などがあります。
このように高齢者は複数の合併症を抱えることが、一般的です。それぞれの疾患に対して最適な治療薬が処方されるため、結果として多くの種類の薬を服用することになります。これが「多剤併用(ポリファーマシー)」です。多剤併用を解消し、高齢者のQOLを向上させるためには、医療従事者と患者・家族が連携して取り組む必要があります。例えば薬剤師による服薬支援や医師による処方内容の見直し、患者さんと家族の方の役割の明確化などがあります。
3-2. 視覚・嚥下能力等の身体機能の低下に起因する服薬方法の支援
視覚・嚥下能力など身体機能が低下することで、飲みにくさからお薬の服用を避けがちになったり、飲み忘れが増えたりします。
3-3. 個々人の生理機能に応じた処方・調剤・服薬
在宅医療を受ける患者さんの多くは、高齢者です。そして、様々な疾患を併発しています。そのため、多剤併用の薬物療法が行われ、重複投薬相互作用のリスクを負っています。
また通院できる患者さんと比べると、運動機能だけでなく、肝機能と腎機能の低下が見られる方が多くいます。そういった患者さんには、体内薬物動態の変動や、全身状態を正確に評価した上での薬物治療が求められます。
4. 在宅薬剤師の効果的事例
4-1. 残薬の整理と服薬遵守の向上
認知機能が低下すると、多くの残薬を抱えてしまうケースがあります。この場合は独居の患者さんでした。在宅薬剤師が訪問し、残薬を整理した上で、飲み忘れを防ぐために服薬カレンダーのセットや一包化を提案しました。その結果飲み忘れが大幅に減少し、患者さん自身で薬の管理ができるようになるなど、QOLが向上しました。
4-2. 医療用麻薬の適正な使用の支援
どんな患者さんでも、初めてのお薬を使用する時は不安があります。特にがんの痛みを和らげるための医療用麻薬は、適用に抵抗される患者さんもいます。このケースでは、患者さんとその家族が「麻薬は怖い」と感じていました。そのため在宅薬剤師が医療用麻薬の用法や安全性について、丁寧に説明を行いました。また正しく使用することで痛みが緩和され、安心して使えることも伝えました。その結果、患者さんと家族の不安を軽減することができました。
4-3. 薬物療法の多職種連携
在宅薬剤師が、他の職種と連携することで効果的な治療を行うことができるケースが多々あります。これは、便秘と皮膚のただれを繰り返していた患者さんのケースです。具体的には薬剤師が看護師と患者さんの情報を共有し、便秘薬の調整や皮膚疾患の薬の変更を医師に提案しました。その結果、症状が以前よりも改善し、患者さんのQOLが向上しました。
5. まとめ
在宅薬剤師は、ケアマネジャーなどの介護職同様、在宅医療の窓口となる重要な仕事です。団塊の世代が後期高齢者になる一方で、病院のベット数は減少しています。医療サービスの質の低下を防ぐためには、在宅医療の早急な仕組み構築が必要不可欠です。
日本の高齢者の医療体制を支えるため、国も地域包括ケアシステムを推進しています。その流れとして、「かかりつけ医」や「かかりつけ薬剤師」があります。
また自宅で診療を受け、薬を配送してもらえる「オンライン服薬指導」も、IT技術を活用した在宅医療の一種といえるでしょう。こういったサービスがますます充実し、サービスの充実と医療費コストの削減がどう両立されていくのか、今後も目を離せません。