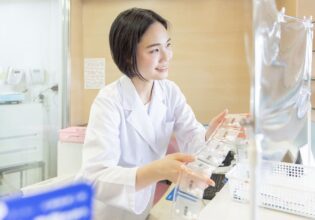2023年時点で、日本全国には薬局が62,828店舗あるといわれています。しかもその店舗数は年々増えており、競争は激化しています。
特に伸びが著しいのが、ドラッグストアです。2021年度の総売上高は8兆5408億円でしたが、2024年には10兆307億円にまで伸びています。その人気の理由は、何でしょうか。MarkeZineのLINEユーザー調査(5,256サンプル)によると、ウェルシアの場合は「立地(37.8%)」「ポイント(37.6%)」「営業時間(25.6%)」でした。つまり、消費者のニーズを上手に取り入れることで店舗を拡大していることがわかります。
薬局は、地域の健康を守る重要な役割を果たしています。例えば超高齢化社会を迎えた日本において、薬局は在宅医療やチーム医療のハブという側面もあります。一方その売上構成比率は、約97%が保険調剤収益といわれています。しかも国は医療費削減の流れから、調剤報酬額を年々減らしています。
では今後の薬局経営で成功するには、どうしたらいいのでしょうか。本記事では、「処方箋集め」「リピート率UP」「業務の自動化」「顧客管理」といったテーマで、最新の薬局経営のあるべき姿を分析します。
1. 処方箋を集める
保険調剤の売上を伸ばすには、処方箋を集める必要があります。どんな種類があり、どのような手段があるのかを、以下に解説します。
1-1. 処方箋の種類
処方箋には、様々な切り口や種類があります。ここでは、薬局経営の視点で代表的なものを以下に記します。
・既存の患者さんの処方箋
・新規の患者さんの処方箋
・急性疾患の処方箋
・慢性疾患の処方箋
1-2. 処方箋を増やす方法
処方箋を増やすためには、大きく2つのポイントがあります。第一に新規の患者さんを増やすということです。例えば陳列を工夫したり、自社サイトやXなどのSNSで、積極的に情報発信します。また地域包括ケアシステムを推進し、地元でイベントを開催して地域住民との良好な関係を築きます。こういったアクションを通じ、新規の患者さんとの接点を増やし、薬局の集客力を強化します。
・ポップアップや商品の陳列の改善による入りやすい薬局作り
・ホームページやSNSでの情報発信による認知度アップ
・地域に根差したイベント開催による地元住民との関係構築
1-3. リピート率を上げる
新規顧客を増やすと同時に重要なのが、患者さんのリピート率を上げることです。言い換えれば、脱落する患者さんを減らすということです。ここで重要になるのは、患者さんの病状や生活習慣を正確に把握し、改善に向けてしっかり伝えるコミュニケーションです。
また電話やLINEの積極的な活用も効果的です。実際に来局予定日に来局されない患者さんに対し架電施策を行うことで、50%近くが再来局することに成功した事例もあります。この施策で重要なのは、単なるプッシュではなく、「体の調子は大丈夫か心配してお電話差し上げました」という姿勢です。このような細やかなアプローチが、リピート率改善アップに結びつきます。
2. サービス力を強化する

2021年8月より、都道府県知事が特定の機能を持つ薬局を認定する制度がスタートしました。薬剤師はただお薬を患者さんにお渡しするだけではなく、”薬のプロ”としてより患者さんの健康に貢献していきます。そのポイントを、薬局経営の視点で解説します。
2-1. 地域連携薬局
知識連携薬局の患者さんにとってのメリットは、利便性が向上することです。例えば、入退院時の医療機関との情報共有が行われます。その結果、在宅医療における一元的対応が可能になります。また必要に応じて外来の患者さんに対し、夜間や休日の対応を行います。
また薬局経営としてのメリットは、地域支援体制加算がより増える点です。地域支援体制加算は2018年の調剤報酬改定で新設され、かかりつけ薬剤師の服薬指導や在宅医療実績、休日・夜間の対応が評価され収益力が向上します。
2-2. 専門医療機関連携薬局
2021年薬機法が改正され、専門医療機関連携薬局制度がスタートしました。例えば患者さんが通う病院や自宅近くの病院など連携し、高度な薬学管理や専門性の高い調剤を提供します。認定要件には、がんに係わる専門性を有する薬剤師の配置が含まれています。
下の図にあるように、専門医療機関連携薬局の認定数は年々増加しています。ただ全国約6万の薬局数においては、まだまだ割合は低い状況です。特に東京19件、神奈川県18件、大阪と北海道で17件と、都市部に集中している傾向があります(2025年3月時点)。今後の普及には、質の高い人材の確保や継続的なキャリア支援、大規模病院と薬局の障壁の解消などが求められています。
2-3. 在宅医療への対応強化
在宅医療に対応している薬局の割合は、43.6%です(2024年8月時点 日本保険薬局協会「調剤報酬等に係る届出の調査報告書」)。在宅医療への取り組みを薬局経営的に検討すると、収益性が大きなポイントです。
個人宅を訪問した場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料として、1回につき650点(6,500円)の報酬が得られます。ただし外来対応と比較すると、移動時間や報告書の作成などの別の業務負担が発生します。さらに以下の追加コストも発生します。
・24時間対応できる体制のための人件費
・在宅医療に対応できるようにするための薬剤師の教育
・無菌調剤室の設置
・緊急対応用の備品の準備
ただ薬局業界の大きな流れとしては、患者さんの高齢化と地域包括ケアシステムの推進を背景に、在宅医療ニーズが高まるのは確実です。では在宅医療業務と収益性を両立させるには、どうしたらいいのでしょうか。その重要ポイントは、ICT(Information and Communication Technology)の活用です。次章でも詳しく述べますが、例えばオンライン服薬指導を導入することで移動時間を節約でき、継続的な薬剤管理がしやすくなります。
2-4. 食品や雑貨販売を新収益源に
2019年の薬価改定により、薬全体の60%以上の薬価が引き下げられました。そうした背景をもとに、調剤薬局では一般用医薬品だけでなく、食品や雑貨を販売し、収益源の多様化を推進する薬局が増えています。
薬局内の物販での重要ポイントは、「お店のコンセプト」や「患者さんのニーズ」に合わせた商品を用意することです。例えば、栄養素を補う「サプリメント」や免疫機能を向上できる「健康食品」です。具体的には、ビタミンCサプリや梅肉エキス、低カロリーのお菓子などがあります。
3. 薬局の業務効率を上げる
薬局経営の重要テーマの一つが、利益体質です。つまり新規獲得とリピート率を上げながら、無駄を省くということです。そのためにはITの活用が欠かせません。この章では、そのポイントを解説します。
3-1. 調剤ロボットの導入
従来人が作業していた業務を機械が代用することで、生産性を上げ、利益率を高めることができます。しかし現実は、薬局における薬剤師は労働集約的な調剤業務が大きな割合を占めています。
そこでそれらの業務の省力化を目的に開発されたのが、調剤ロボットです。例えば首都圏のドラッグストアでは調剤ロボットを導入することで、調剤業務の90%を自動化しています。それによって従来よりもかかりつけへシフトし、患者さんとのコミュニケーションに注力できます。
3-2. AI監査システムの導入
薬局のAIを使った監査システムは、調剤過誤のリスクを減らし、薬剤師の業務を効率化することができます。具体的には、画像認識やバーコード、重量計測などの技術を用い、薬剤の種類や数量を正確に識別します。そして処方箋データと照合することで、薬剤の取り間違いや数量ミスを検出します。また調剤薬品をカメラで撮影し、その画像をクラウド上に保存することも可能です。
AI監査システムの種類には、Anthropic社が提供するAIの未知の危険性を発見・評価するものや、調剤監査システムのように特定の業務におけるヒューマンエラー防止に特化したもの、さらにはAIを活用したセキュリティ管理策のフレームワークなど、様々な種類があります。
3-3. 調剤分包機の導入
調剤分包機は、薬を一袋ずつ均等に分ける手撒き作業を自動化し、薬剤師の業務負担を大幅に軽減します。また処方薬の種類や数が多い際の服薬漏れを防止し、作業時間を短縮することで患者さんの待ち時間を減らせるメリットもあります。機種によっては、汚れ検知機能や不足錠剤を知らせてくれるAIを搭載しているものもあります。
3-4. LINEを活用した顧客管理
LINEは9,500万人が利用しており、処方箋の送信受付やオンライン服薬指導、服薬フォローにも便利です。例えば電子お薬手帳アプリの場合、インストール方法を高齢の患者さんに説明するのは大変です。またスマートフォンの機種変更に伴い、アプリが削除されることもあります。しかしLINEはほとんどの方が日常のコミュニケーションで利用しており、すぐに使用してもらえるというメリットがあります。例えば「つながる薬局」サービスには、以下の機能があります。
・処方箋の受付と待ち時間対策
・電子処方箋対応
・オンライン服薬指導とクレジットカード決済
・服薬のToDo管理(例.選択式の回答)
・健康やお薬に関する相談
4. 薬剤師の採用力を強化する
薬局のサービス力を支えるのは、人材です。2020年以降の薬剤師の有効求人倍率は3.3倍で、以前と比べると低くなってきています。薬剤師を採用するための人気の手法は、薬剤師向けの求人サイトや人材紹介を活用する方法です。「マイナビ薬剤師」や「ファルマスタッフ」、「薬キャリAGENT」などが有名なサービスです。
ただし、それらは競合も同じ方法を活用しています。そうした中で差別化を図り、優秀な人材を採用するにはどうしたらいいのでしょうか。それは、転職を希望する薬剤師が「どんな情報を求めているか」というニーズに応えるという視点が重要です。例えば「お給料」や「人間関係」、「キャリア形成」など、転職動機には様々な種類があります。そういった動機に応える情報を薬局のホームページに掲載することが、採用の成功に繋がります。また共感性を高めるため、その情報をアピールできる現場スタッフのインタビューは効果的です。
5. 薬局経営の成功事例紹介

5-1. ITを活用し商品動向や待ち時間短縮も
A薬局では、レセプトコンピューターと連動したPOSシステムを導入しました。そうすることで、会計管理だけでなく、患者さんの薬歴管理と服薬指導の一元管理が可能になりました。また地域における売れ筋商品の把握も容易になりました。
また多くの人が使っているLINEの公式アカウントを開設し、「処方箋受付」や「お薬の相談」などのオンライン化を推進しました。そうすることでお客様の待ち時間が大幅に短縮できただけでなく、スタッフも仕事の効率化が図れました。
スタッフの中には現在育児中の薬剤師がいましたが、無理なく働けるようになりました。またアルバイトのマネジメントもより効率的になり、人件費の削減も実現しました。

5-2. 厳選商品を充実させて相談も積極的に
B薬局は、現在1つの駅周辺に5店舗展開し、地域シェアは30%を超えています。調剤、在宅訪問だけでなく日用品の充実や、地域の方に参加して頂けるイベントも開催しています。また、PCやスマートフォンなどのデジタルテクノロジーを取り入れるICT化(Information Communication Technology)を推進しています。そうすることで、店舗間の情報共有が容易になりました。
大きな転換点は、3店舗目の出店以降です。採用業務なども増え、患者さんとのコミュニケーションの時間が取れなくなりました。そこで独自の強みを強化するため、専門家の評価が高い「こだわりの商品」の発掘を推進しました。日本薬局協励会に入り、優良医薬品について情報収集しました。また「人体の働きと医薬品」「主な一般用医薬品とその併用」などの研修も受けました。高度な知識とクラウド上の情報共有、患者さんとの相談が、満足度を向上させました。その結果、コロナ禍にも関わらず、増収増益を実現しました。
5-3. 医薬品ネットワークでコスト削減
C薬局は、コスト削減が経営の重要テーマでした。その解決策として、4年前に医薬品ネットワークに加入しました。「在庫管理」や「不動在庫処理」、「卸会社ごとの医薬品購入や支払い業務」「後発品選定」を効率化するためです。
医薬品ネットワークは、「価格交渉」だけでなく、卸の取引先が多いことによる「豊富な商品ラインナップ」も魅力でした。流通改善が経営効率化につながった結果、より地域の患者さんと向き合える時間も増えました。
5-4. ITマーケティングで集客し新規顧客獲得に成功

病院のそばにある門前薬局は、医療機関で受診した患者さんが自動的に訪れます。D薬局はそういった立地ではなかったため、独自に新規顧客を集客する必要がありました。そこで、Webマーケティング会社にホームページのリニューアルを依頼しました。ポイントは、大きく2つありました。まず「薬局+地域名」「病名+地域名」といったターゲットが検索しそうなキーワードを選定し、Googleでの上位表示を目指しました。
次に訴求力を強化するため、「かかりつけ薬局」としてのサービス強化です。独自商品や待ち時間の削減、Q&Aコンテンツなどを充実させました。施策の結果、患者さんの来局数が大幅に増加し、収益力が大幅にアップしました。今後はLINEを活用した顧客管理を充実させ、オンライン相談も含めて、より患者さんとの距離を近づける予定です。
6. 薬局経営に役立つ本について
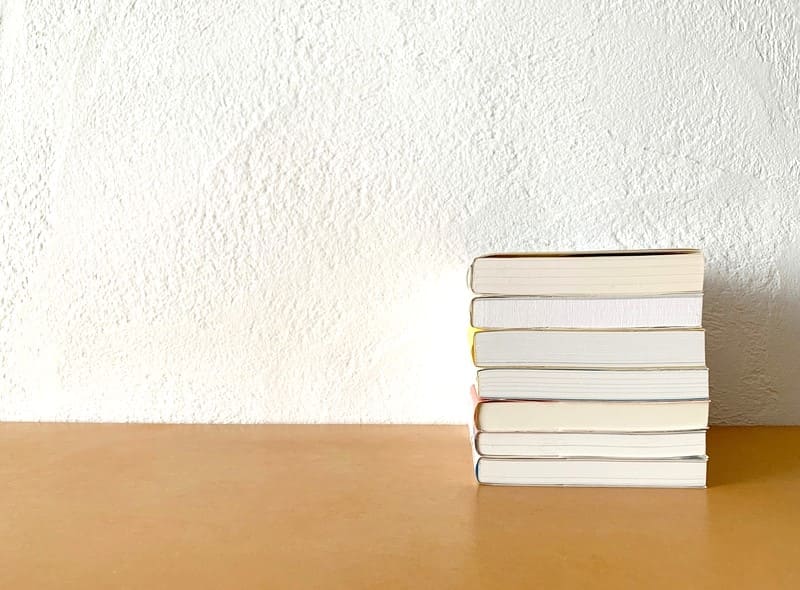
6-1. 成功する調剤薬局経営
この「成功する調剤薬局経営」は、「これから薬局経営を始めてみたい」「2軒目を手掛けたいが情報がない」という方におススメです。見出しには、「勝てる薬局・勝てない薬局」「ドクターとどう付き合うか」「スタッフとどう付き合うか」といった興味深い構成になっています。
また筆者は、サラリーマン時代に医薬品卸売業、調剤薬局チェーンで店舗開発業務を経験しています。その時培ったノウハウが、調剤薬局経営用に編集されています。
6-2. ロボット薬局
「ロボット薬局」の表紙の帯には、「大手通販ネットショップの業界参入により薬局はかつてない淘汰の危機に直面する!」というフレーズがあります。またピッキング作業をロボットに任せて、薬剤師を対人業務に専念させるといった鋭い指摘もされています。
見出しには、「2021年の調剤薬局の倒産は過去最多」「DXで後れを取る薬局業界」「Amazon薬局という黒船」といった興味深い内容が盛り込まれています。
6-3. 保険薬局Q&A 令和4年版
この「保険薬局Q&A 令和4年版」は、書名の通り薬局業務のポイントをQ&A形式で解説してくれています。例えば「処方箋受付」や「後発医薬品」、「訪問薬剤管理指導」等の疑問が解消されます。
令和4年版には、「オンライン服薬指導の最新知識」や「事務スタッフの教育」なども掲載されています。『薬剤師の本でおすすめは?スキルアップできる人気の本をご紹介!』でも紹介していますので、是非参考にして下さい。
7. まとめ
薬局経営は、処方箋集めや新規顧客の獲得、リピート率の向上、業務の自動化、人材採用など、多くの重要な要素で構成されています。それらを優先順位をつけながら、並行して改善していくことが必要不可欠です。
まずはテーマごとにToDo項目を洗い出し、KPIを設定しましょう。最終目標までの定量的な数値を設定し、メンバーと共有することで、努力すべき方向性が見えてきます。ここで大切なのは、過去の実績に基づいた整合性のある目標設定数字です。そうすることでメンバーのモチベーションも上がり、達成する確度も高まります。
その流れの中で改善のスピードを推進するのは、成功体験です。最初は小さな成功体験でも、いずれ大きな成果につながることがよくあります。そのパターンをどれだけ体験し、共有できるかがとても重要です。