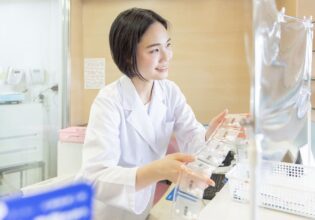化学療法とは、抗がん剤を用いて、癌を治療することです。抗がん剤には、癌細胞の拡大を抑えたり、再発や他への転移を防ぐ効果があります。そのため転移の可能性がある時や、広範囲な治療が求められるな血液やリンパの癌などにも行われます。そしてがん薬物療法に特化した知識を用いて質の高い薬物療法を提供するのが、がん専門薬剤師です。
薬剤のパターンとしては、一種類だけ使う場合と数種類を組み合わせる場合があります。お薬の種類としては、飲み薬や注射、点滴などがあります。また化学療法は、抗がん剤単体だけでなく、手術や放射線療法と組み合わせる治療方法もあります。その場合、治癒率が高まることが判明しています。
本記事では、化学療法について、詳しく解説します。
Contents
1. 化学療法とは

1-1. 全身治療ができる化学療法
化学療法とは、がん細胞を直接攻撃する抗がん剤(化学療法剤)を用いた治療方法です。薬物療法とも呼ばれます。
手術治療や放射線治療は、癌に対する直接的で局所的な治療です。一方化学療法は、体の広い範囲に効果が波及することが期待できます。抗がん剤が投与されると、血液中に入り全身を駆け回ります。
そして細胞周期に干渉し、がん細胞のDNAや、細胞分裂に必要な酵素などを標的にします。その結果、がん細胞の増殖を抑制し、アポトーシス(プログラムされた細胞死)させる効果があります。また当初の治療の効果が落ちてきた場合は、別の抗がん剤治療に切り替えます。
このように、化学療法は体のどの場所にがん細胞があっても、それを破壊するという効果があります。一般的には、手術や放射線療法が適応にならない場合に、抗がん剤などの薬物療法を行います。
ただ抗がん剤は、がん細胞だけでなく、正常な細胞に対しても作用します。つまり抗がん剤の投与量を増やすとがん細胞への効果は増しますが、正常細胞への副作用も強くなります。
1-2. 化学療法の種類
1-2-1. 細胞障害性抗がん剤
細胞障害性抗がん剤は、がん細胞の増殖を抑える化学療法薬の一種です。例えば細胞分裂の盛んな細胞を攻撃する事で、がん細胞の増殖を抑制します。しかし正常な細胞も細胞分裂を行うため、副作用が現れる可能性もあります。またその作用機序によって、いくつかの種類に分類されます。
① アルキル化薬…DNAにアルキル基を付加し、DNAの複製を阻害します
② 代謝拮抗薬…DNA合成に必要な物質と類似の構造を持ち、DNA合成を阻害します
③ 抗腫瘍性抗生物質…DNAに結合し、DNAの複製や転写を阻害します
④ 植物アルカロイド…微小管に作用し、細胞分裂を阻害します
⑤ トポイソメラーゼ阻害薬…DNAの構造変化に関わる酵素を阻害し、DNAの複製を阻害します
また主な副作用としては、以下のようなものが挙げられます。
① 骨髄抑制…白血球や赤血球、血小板の減少により、感染症や貧血、出血のリスクが高まります
② 消化器症状…吐き気や嘔吐、食欲不振、口内炎、下痢などが起こることがあります
③ 脱毛:…頭髪だけでなく、全身の体毛が抜けることがあります
④ 倦怠感…全身のだるさや疲れやすさを感じることがあります
⑤ 生殖機能への影響…卵巣や精巣の機能が低下し、不妊となることがあります
1-2-2. 分子標的薬
分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わる特定の分子(タンパク質など)を標的とし、その働きを阻害し、がん細胞の増殖を抑制します。標的となる分子は、がんの種類によって異なります。分子標的薬の種類を以下に記します。
① 抗体医薬…がん細胞の表面にある特定の分子に結合し、がん細胞の増殖を阻害したり、免疫細胞による攻撃を誘導したりします
② 低分子化合物…がん細胞の内部にある特定の分子に結合し、その働きを阻害します
③ 血管新生阻害薬…がん細胞への栄養供給を担う血管の新生を阻害することで、がん細胞の増殖を抑制します
④ 植物アルカロイド…微小管に作用し、細胞分裂を阻害します
⑤ がんシグナル伝達阻害薬…がん細胞の増殖に関わるシグナル伝達経路を阻害することで、がん細胞の増殖を抑制します
分子標的薬の特徴について、以下に記します。
① がん細胞に特異的に作用するため、副作用が比較的少ない
② がんの種類によっては、高い治療効果が期待できる
③ 遺伝子検査などによって、患者さんのがん細胞に合った分子標的薬を選択できる
また副作用については、発疹やかゆみなど皮膚障害、下痢や吐き気など消化器症状、高血圧、血栓や出血などの血管障害が挙げられます。
1-2-3. 免疫チェックポイント阻害薬
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞に対する免疫反応を活性化させることで、がんを攻撃する新しいタイプの抗がん剤です。従来のがん治療薬とは異なる作用機序を持ち、一部のがん種では非常に高い治療効果を示すことから、近年注目を集めています。
私たちの体には、がん細胞などの異物を排除する免疫システムが備わっています。しかし、がん細胞は免疫システムからの攻撃を回避するために、「免疫チェックポイント」と呼ばれる仕組みを利用します。免疫チェックポイント阻害薬は、この免疫チェックポイントを阻害することで、免疫細胞ががん細胞を攻撃できるようにします。その種類について、以下に記します。
<抗PD-1抗体>
PD-1は、T細胞と呼ばれる免疫細胞の表面にある分子です。がん細胞のPD-L1という分子と結合することで、T細胞の働きを抑制します。抗PD-1抗体は、PD-1とPD-L1の結合を阻害し、T細胞の活性化を促します。
<抗PD-L1抗体>
PD-L1は、がん細胞や一部の免疫細胞の表面にある分子です。PD-1と結合することで、T細胞の働きを抑制します。抗PD-L1抗体は、PD-L1とPD-1の結合を阻害し、T細胞の活性化を促します。
<抗CTLA-4抗体>
CTLA-4は、T細胞の表面にある分子で、T細胞の活性化を抑制します。抗CTLA-4抗体は、CTLA-4の働きを阻害し、T細胞の活性化を促します。
免疫チェックポイント阻害薬の特徴は、従来のがん治療薬とは異なる作用機序を持つため、他のがん治療薬が効かないがんにも効果が期待できます。また免疫システムを活性化するため、治療効果が持続することがあります。しかも、一部のがん種では、長期生存が期待できます。
1-2-4. ホルモン療法
ホルモン療法は、ホルモンの影響を受けて増殖するがんに対して、ホルモンの働きを抑えることでがんの増殖を抑制する治療法です。主に乳がん、前立腺がん、子宮体がんなどの治療に用いられます。
がん細胞の中には、特定のホルモンと結合する受容体を持っているものがあります。これらの受容体にホルモンが結合すると、がん細胞の増殖が促進されます。ホルモン療法は、以下のいずれかの方法でホルモンの働きを抑え、がん細胞の増殖を抑制します。
・ホルモンの産生を抑制する
・ホルモンが受容体に結合するのを阻害する
ホルモン療法は、使用する薬剤や作用機序によって、いくつかの種類に分類されます。
<抗エストロゲン薬>
エストロゲン受容体に結合し、エストロゲンの働きを阻害します。主に乳がんの治療に用いられます。
<アロマターゼ阻害薬>
エストロゲンの産生に関わる酵素を阻害し、エストロゲンの産生を抑制します。主に閉経後の乳がんの治療に用いられます。
<LH-RHアゴニスト/アンタゴニスト>
性腺刺激ホルモンの分泌を調節し、性ホルモンの産生を抑制します。主に前立腺がんの治療に用いられます。
<抗アンドロゲン薬>
アンドロゲン受容体に結合し、アンドロゲンの働きを阻害します。主に前立腺がんの治療に用いられます。
<プロゲスチン製剤>
プロゲステロン受容体に作用し、ホルモンバランスを調整します。主として子宮体がんの治療に用いられます。
ホルモン療法は、がん細胞に特異的に作用するため、細胞障害性抗がん剤に比べて副作用が比較的少ないのが特徴です。内服薬や注射薬など、投与方法が比較的簡便で、長期に渡って治療を継続できます。副作用としては、ほてりや発汗などのホットフラッシュや性機能障害、骨粗鬆症などが挙げられます。
1-3. がんの進行形態と治療方法
一般的に早期のがんは、体の臓器のある部位に限定して発生し、増殖します。そして進行すると、全身に広がります。これを、転移といいます。
外科療法や放射線療法は、局所的ながんには強力な治療方法です。しかし、既にがんが全身に転移している場合や、白血病にように診断時から病変が全身に及んでいる場合、全身に放射線療法を行うことはできません。その理由は、副作用が強すぎるからです。また手術によって、体中のがん細胞を除去することは不可能です。
このように体中に広がったがん細胞を治療するためには、化学療法は効果的な治療方法といえます。また抗がん剤一覧ページでは、現在の医療現場で使用されている抗がん剤やホルモン剤が紹介されています。
1-4. 化学療法に期待されるもの
化学療法は、がん細胞の増殖を抑えたり、がんを縮小させたり、症状の緩和を目的に行われる治療法です。期待される効果について、以下に記します。
1-4-1. 治癒
白血病や悪性リンパ腫などの血液がんや早期のがんでは、化学療法のみで完全に治癒することを目指します。また手術や放射線療法と組み合わせることで、治癒の可能性を高める場合があります。
1-4-2. 延命
進行がんや転移がんの場合、化学療法によってがんの進行を遅らせ、生存期間を延長させることを目指します。また症状を緩和し、生活の質(QOL)を維持しながら、より長く生きることを目標とします。
1-4-3. 症状の緩和
がんによる痛みや吐き気、食欲不振などの症状を和らげ、患者さんの苦痛を軽減します。またQOLの向上を目的として、緩和ケアの一環として行われる場合があります。
1-4-4. 術前・術後補助療法
手術前に化学療法を行うことで、がんを小さくし、手術で完全に切除できるようにします。また手術後に化学療法を行うことで、目に見えない微小ながん細胞を死滅させ、再発のリスクを低減します。
2. 化学療法のパターンとは

2-1. 化学療法のみを実施する場合
この場合の目的は、がんの進行を遅らせることです。また血液癌など手術が要らない癌の治療の場合は、完全な治癒を目指します。
2-2. 放射線療法と併用する場合
化学療法と放射線療法を併用する治療法は、がん治療において重要な選択肢の一つです。以下にポイントを記します。
2-2-1. 治療効果の増強
化学療法は全身のがん細胞に作用し、放射線療法は局所のがん細胞に作用します。これらを組み合わせることで、全身と局所の両方に対して効果的にがん細胞を攻撃することができます。また化学療法薬には放射線感受性を高める作用を持つものがあり、放射線療法の効果を増強できます。
2-2-2. 手術の代替
手術で切除が難しい進行がんや、臓器の温存を希望する場合に、手術の代替として用いられます。
2-2-3. 併用療法の種類について
① 同時化学放射線療法…化学療法と放射線療法を同時に行う方法です。治療効果が高い反面、副作用も強く出やすい傾向があります。
② 術前・術後化学放射線療法…手術前または手術後に、化学療法と放射線療法を行う方法です。手術の補助的な役割を果たし、再発リスクを低減することを目的とします。
2-2-4. 併用療法の副作用について
① 骨髄抑制…白血球や赤血球、血小板の減少により、感染症、貧血、出血のリスクが高まります
② 消化器症状…吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎などが起こることがあります
③ 皮膚炎…放射線照射部位の皮膚に、赤み、かゆみ、痛みなどが生じることがあります
2-3. 手術と併用する場合
手術前は、まず化学療法で大きな癌を小さくします。そして、手術で全てを取り除けるようにします。手術で切り取る部分を小さくするので、出血が少なくなり、体への負担を軽減できます。
手術後に、目視できない小さな癌が残っている可能性があります。それが再発・転移をしないように、化学療法で予防します。同時に、手術で取り除けなかった癌の増殖を抑えます。
3. 自宅でもできる外来化学療法について

化学療法の多くは、以前は入院による治療でした。ところが最近では、新しい抗がん剤や、副作用を抑える薬、長期間の投与に適した医療機器が登場しています。
そういったものを組み合わせることにより、外来や自宅で化学療法を実施することができるようになりました。患者さんのがんの種類にもよりますが、お仕事を続けながら、化学療法でがん治療を行う人が増えています。外来化学療法の基本的な特徴を、以下に記します。
3-1. 通院しながら治療を継続できる
週に1回や2週間に1回など、治療スケジュールに合わせて通院します。数時間の点滴や短時間の注射など、病院滞在時間は比較的短い傾向があります。また入院が不要なため、日常生活を維持しやすいというメリットもあります。
3-2. 自宅で投与可能な抗がん剤の利用
3-2-1. 経口抗がん剤(飲み薬)
飲み薬の経口抗がん剤には、カペシタビン(ゼローダ)やS-1(ティーエスワン)があります。これらを自宅で服用しながら、治療を続けることができます。ただし、副作用管理のために定期的な診察が必要です。
3-2-2. 持続注入ポンプ(携帯型の注入ポンプ)
小型のポンプを装着し、数日間かけてフルオロウラシル(5-FU)の持続投与(FOLFOX療法やFOLFIRI療法)を持続的に投与します。一定期間が経過すると、病院でポンプを外します。
3-3. 自宅での治療における注意点
3-3-1. 副作用の管理
化学療法では、吐き気や下痢、口内炎などの副作用が出ることがあります。例えば症状が悪化した場合、すぐに病院へ連絡する必要があります。また白血球減少による感染症のリスクがあるため、体調管理が大切です。
3-3-2. 服薬管理を徹底する
経口抗がん剤の場合、決められた時間や用量を守ることが大切です。飲み忘れや誤った服薬がないように、家族のサポートがあるとより安心です。
3-3-3. 緊急時の対応について
38℃以上の発熱や激しい吐き気、下痢などが起こったときは、すぐに医療機関へ連絡しましょう。また自宅近くの病院や緊急連絡先を把握しておくことが大切です。
4. 抗がん剤の種類について

4-1. 代謝拮抗剤
代謝拮抗剤は、癌細胞に多く含まれている酵素を利用し、増殖を押さえ込む薬です。まず抗腫瘍効果を発揮する前の薬として投与されます。これががん細胞の中にある酵素の働きを受けて活性化され、抗がん剤として機能します。
この代謝拮抗剤は、がん細胞が分裂するときに効果を発揮します。そのため、それぞれのがん細胞が分裂するタイミングを狙って、長時間かつ持続的に薬を投与する必要があります。
4-2. アルキル化剤
アルキル化剤は、DNAに働く薬です。DNAは、核酸と呼ばれる塩基が対になって二本の鎖状に結合し、せん状の構造を作っています。アルキル化剤は、強力で異状な結合をDNAとの間に作ります。その結果、DNAの遺伝情報が障害され、DNAも損傷を受けます。その結果、細胞が分裂増殖するときにアルキル化剤が結合した場所でDNAはちぎれ、がん細胞を死滅させる効果があります。
4-3. 抗腫瘍性抗生物質
抗腫瘍性抗生物質は、土壌に含まれる微生物から作られたものが原型です。もともとは細菌に対する抗生剤と同じく、がん細胞に対しても選択的に働く抗生物質があるのではないかという想定で開発されました。細菌やかびに効く構造を持った抗生物質の化学構造を変化させ、がん細胞を死滅させる機能を持ったものもあります。
4-4. 微小管作用薬
微小管作用薬は、細胞分裂に必要な微小管の機能を停止させることで、がん細胞を破壊します。「ビンカアルカロイド」と「タキサン」の二種類の化学物質に分類されます。また神経細胞の働きにも重要な役割を果たしており、手足のしびれなど神経障害が出る可能性があります。
5. まとめ
化学療法は、体全体に効果が行き渡る抗がん剤を使った治療方法です。
ただ使用するお薬によっては、効能や副作用が異なります。お薬によっては、白血球の減少や血小板減少、貧血、吐き気といった副作用が起こります。
また化学療法は、患者さんの病気の状況やライフスタイルによって、目的や実施するタイミングは異なってきます。
患者さんの病状を正確に把握した上で、最適な選択肢を考慮することが、とても大切です。