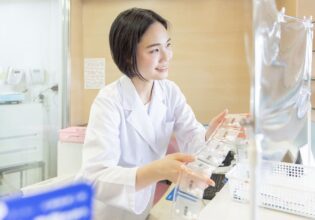オンライン服薬指導とは、薬剤師がスマートフォン等のデバイスを活用し、ビデオ通話で実施する服薬指導です。薬局まで行かなくても、好きな時間と場所で服薬指導を受けれるというメリットがあります。また自宅で受ける場合、人の目を気にしなくて良いという特徴もあります。
超高齢化社会を迎えた日本では、通院が困難な患者さんへのケアは重要なテーマです。また障碍者の方や遠隔地在住の方にも、オンライン服薬指導は便利です。しかも対面接触を避けることができるので、感染症リスクを低減できます。また薬局経営的には、時間や人員の有効活用につながります。
最新のトレンドとしては、アプリとの連携やLINEのチャット活用があります。例えば服薬指導後のフォローアップや質問受付を、チャットで対応する薬局が急増しています。また2023年に開始した電子処方箋制度とオンライン服薬指導の統合が進んでいます。本記事では、オンライン服薬指導について詳しく解説します。
1. オンライン服薬指導について

オンライン服薬指導を受ける患者さん
オンライン服薬指導とは、薬剤師からビデオ通話で服薬指導を受けられるサービスです。例えば、スマートフォンやタブレッド、パソコンを使って行われます。今までの服薬指導は、薬局を訪れて薬剤師から対面で説明を受ける必要がありました。しかしオンライン服薬指導では、自宅などで服薬指導を受けることができます。そうすることで、時間や場所の制約を受けずに、服薬指導を受けることができます。
1-1. メリットについて
具体的なメリットについて、以下に記します。
① 時間や場所を選ばずに、服薬指導を受けることができる
② 薬局までの移動時間や交通費がかからない
③ 待ち時間が要らなくなる
④ プライバシーを守ることができる
⑤ 服薬指導内容を記録し、確認できる
1-2. デメリットについて
具体的なデメリットについて、以下に記します。
① スマートフォンやパソコンが必要になる
② インターネット環境が必要になる
③ 対面での服薬指導よりも、時間が短くなる場合がある
1-3. 対象者について
オンライン服薬指導の対象者について、以下に記します。
① 重度の病気や障害がある方
② 子どもの育児や親の介護で忙しく、薬局まで通うのが難しい方
③ 遠隔地にお住まいの方
2. オンライン服薬指導の要件

オンライン服薬指導を受ける患者さん
オンライン服薬指導を実施するには、「法令上の要件」と「実務上の要件」を満たす必要があります。ここでは、この2点について解説します。
2-1. 法令上の要件
① 薬剤師が、医薬品医療法及び薬剤師法に基づいて服薬指導を行う
② 患者さんの同意を得た上で実施する
③ プライバシーの保護に配慮した環境で行う
④ 服薬指導の内容を記録し、保存する
2-2. 実務上の要件
2-2-1. 通信環境について
オンライン服薬指導では、映像と音声の双方向の通信が安定したインターネット環境が必要になります。これは、薬剤師が患者さんと円滑なコミュニケーションを図るためです。また昨今の個人情報の安全上、セキュリティ対策が施された通信環境が理想です。
2-2-2. 情報通信機器について
薬剤師と患者さんが画面を通じて対面で話すために、カメラとマイクを備えた機器が必要です。また円滑に話すために、画面がある程度大きく、十分な解像度が必要です。
2-2-3. 薬剤師について
オンライン服薬指導に関する研修を受講していることが求められます。また情報通信機器の操作ができ、プライバシー保護に関する知識があることも求められます。
3. オンライン服薬指導の流れ

3-1. 医療機関での受診
対面もしくはオンライン診療で、医師の診察を受けます。この時希望する患者さんは、医師に伝える必要があります。オンライン服薬指導に医師が同意した場合、処方箋が発行されます。また一部の医療機関では、オンライン診療のみで処方箋を発行し、オンライン服薬指導を行うところもあります。
3-2. オンライン服薬指導の予約
患者さんは医療機関から処方箋を受け取ると、希望する薬局でオンライン服薬指導の予約を取ります。予約時には、以下の情報が必要になります。
① 氏名
② 住所
③ 電話番号
④ 処方箋情報(医療機関名、医師の名前、処方日、処方内容他)
⑤ 服薬指導の希望日
⑥ 使用機器(パソコン、スマートフォン、タブレットなど)
3-3. 処方箋の提出
予約した日時に、オンライン服薬指導の準備をします。例えば、事前に薬局から送られてきた指示に従って処方箋を提出します。処方箋の提出方法は、郵送やFAX、画像送信などがあります。
3-4. オンライン服薬指導の実施について
予約した当時、薬剤師からビデオ通話がかかってきます。ビデオ通話において患者さんは、以下の内容について説明を受けます。
① 処方された医薬品の飲み方や用法、用量について
② 医薬品の効果や副作用について
③ 服薬中の注意すべきこと
④ 患者さんの状況に合わせた服薬指導について
3-5. 決済と薬の受け取りについて
オンライン服薬指導の終了後、薬局から医薬品代金の請求が行われます。支払い方法は、薬局によって異なります。例えば、銀行振込やクレジットカード払い、コンビニエンスストア払いなどがあります。
そして医薬品は、自宅配送か、薬局での受け取りのどちらかを選択できます。近年は、医療ベンチャー企業と提携し病院で処方された薬を患者さんに届けるサービスがあります。 例えば患者さんはオンライン診療を受けて薬の配達を希望すれば、病院は処方薬を配達員に渡し、自宅や職場に30分程度で配達されます。
3-6. 服薬後のフォローアップについて
オンライン服薬指導後も、患者さんは薬剤師から定期的に服薬状況の確認やフォローアップを受けることができます。
4. 薬局内のスタジオ設置について
4-1. スタジオ設置の目的と必要性
スタジオ設置の大きな目的は、患者さんが安心して話せるプライバシーの確保です。例えばオンライン服薬指導の内容や、個人情報の漏洩を防ぐことができます。また騒音が入らず、通信が途切れない環境を確保することができます。クリアな音声を実現することで、対面と同じレベルの質の指導が実現できます。
4-2. スタジオの場所の選定について
スタジオの場所は、薬局内の業務音や会話が入り込まない独立した個室が理想です。また患者さんの声が外部へ漏れないような防音対策も大切です。さらに第三者が容易に立ち入らないような配慮も必要です。
4-3. 必要な通信環境や映像音響機器
安定したインターネット回線は必要不可欠です。最も安定していて推奨されるのは、有線LAN接続です。例えばWi-Fiを利用する場合は、他の機器との干渉や電波の安定性を確認しましょう。また患者さんが薬剤師の表情をクリアに確認できるよう、高解像度のウェブカメラを選びましょう。広角レンズである必要はありませんが、画角調整ができると便利です。例えば薬剤師の声がクリアに伝わり、外部の音を遮断できるヘッドセットは、集中して指導を行うことができます。
4-4. 運用のポイント
オンライン服薬指導は、「目線の合わせ方」や「声のトーン」、「身振り手振り」がとても大切です。スタジオの中で練習することで本番のミスを防ぐことができます。また予約システムを導入することで、患者さんの利便性が向上し、薬剤師のスケジュール管理も容易になります。
5. オンライン服薬指導の成功事例
5-1. アインホールディングスの在宅医療患者へのオンライン指導
大手調剤薬局グループのアインホールディングスでは、訪問看護と連携し、在宅医療患者にオンラインで服薬指導を実施しました。その結果患者さんの生活環境に即したアドバイスが可能になり、服薬アドヒアランスが向上しました。成果としては高齢患者の服薬ミスが減少し、家族との情報共有もスムーズになりました。
5-2. クオール株式会社の地方の慢性疾患患者向け遠隔指導
地方在住の高血圧・糖尿病患者を対象に、クオール株式会社のかかりつけ医と連携したオンライン服薬指導を実施しました。また遠方の患者も定期的な服薬支援を受けられる体制を構築しました。成果としては、通院負担の軽減や処方薬の自己中断率が減少しました。また医師と薬剤師、患者さんの三者連携が深化のも大きな特徴です。
5-3. SOKUYAKU(ソクヤク)サービスの都市部の若年層ユーザー向け
スマホアプリを活用し、薬局に行かずに服薬指導・処方薬の配送を完結させるサービスです。働く若年層や育児中の家庭で利用が拡大しています。例えば予約から指導、配送までアプリ内で完結し、オンライン指導後のリマインド通知で服薬率がアップします。また利用者の継続率が高く、口コミ評価が良好なのも大きな特徴です。
5-4. アメリカCVSヘルスのTelePharmacyプログラム
米大手薬局チェーンCVSが、過疎地に住む慢性疾患患者向けにオンライン薬剤師と相談できるシステムを導入しました。医療格差の解消を目指した取り組みで、医療アクセスのないエリアでも指導実施可能になりました。また服薬遵守率が従来より20%以上向上しました。
5-5. インド1mg社のデジタル薬局プラットフォーム
1mgはオンライン診療、服薬指導、処方薬配送を一体化したプラットフォームです。経済的制約のある層にも適切な薬学的支援を提供できるという特徴があります。例えば都市と農村部の医療格差を縮小し、AIを活用した服薬スケジュール提案で治療継続率が向上しました。デジタル・ヘルス政策の先進モデルとして注目されています。
6. まとめ
オンライン服薬指導の利用者は、今後ますます増加していくと予想されています。例えば2022年4月の改正薬機法施行ではオンライン服薬指導の要件が緩和され、より利用しやすくなりました。
今後も政府や医療関係団体による普及啓発活動だけでなく、システムの利便性向上などが進められるでしょう。その結果、より多くの患者さんが利用できる環境の整備が期待されています。
同時に、服薬指導の個別化や患者さんのニーズに合わせた情報提供など、より質の高い服薬指導を提供するための取り組みが求められます。