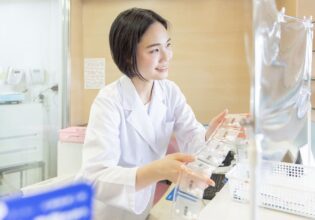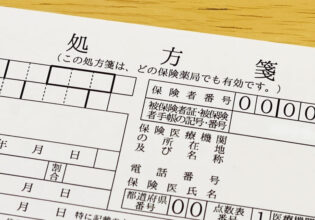薬剤師以外の一包化は、一定の条件を満たせば可能です。その条件とは、「薬剤師の目が届く範囲での実施」です。この考えは、2019年4月2日に厚生労働省が都道府県に通知しました。
この「調剤業務のあり方について」の通知では、薬剤師以外の者が実施する可能な業務の基本的な考え方が明示されています。基本的には、調剤に関して最終的な責任は薬剤師が負います。しかし一包化やピッキングは、薬剤師以外の人間が担当しても差し支えありません。
では、なぜこのような動きが起こってきたのでしょうか。その背景には、国が推進する「薬剤師の対人業務への転換」があります。さらにいうと、薬剤師の人数の増加に関わらず、現場での薬剤師不足問題があります。つまり薬剤師の業務範囲が広すぎることで、現場が回っていないのです。
そのため、薬剤師は本来の専門性を生かした薬物療法業務集中する必要があります。同時に、かかりつけ薬剤師としての機能を強化することも求められています。
本記事では、薬剤師以外の一包化や薬剤師業務のあり方などについて解説します。
Contents
1. 薬剤師以外の一包化について

2019年4月2日、厚生労働省は「調剤業務のあり方について」を都道府県に通知しました。これは、薬剤師以外の者ができる業務に関する基本的な考えが整理されたものです。
基本的に、薬剤師が調剤に最終的な責任を担うのは従来と同じです。その上で、医療事務など薬剤師以外のスタッフができる業務が設定されました。それらを、以下に記します。
① 薬剤師以外の者が行う業務は、薬剤師の目の届く場所で行う
② 薬剤師の薬学的知見と処方箋に基づき、薬剤の品質に影響がなく、患者さんに危害が及ばないようにする
③ 業務を担うスタッフが、独自で判断する余地のない機械的作業に限る
例えば具体例として、処方箋に記された医薬品の必要量を取り揃えることや、薬剤師の監査前の一包化した薬剤の数量確認などがあります。しかし以下の業務は、薬剤師の途中確認があっても薬剤師以外の者が行うと薬剤師法第19条に違反することになります。
・薬剤師以外の者が、軟膏剤、水剤、散財等の医薬品を直接計量、混合すること
薬剤師法第19条は、以下のように定めています。
薬剤師法第19条
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。
また調剤行為には該当せず、薬剤師以外の人間でも行える業務としては、以下が挙げられています。
① 納品された医薬品を調剤室内の棚に収める
② 調剤済みの薬剤を患者さんのお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる
③ 電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する
④ 薬局内に調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合、先に服薬指導等を薬剤師が行い、患者さんの居宅等に調剤した薬剤の郵送等を行う
先述の通知では、薬局開設者に対して、業務手順書の手順や研修の実施を求めています。
2. 現場で行われる具体的作業について
では実際の薬局の現場で、薬剤師以外のスタッフができる業務の詳細についてみていきたいと思います。各業務について、以下に解説します。
2-1. PTPシートに包装された医薬品を取りそろえる

PTP(press through pack)シートは、カプセルや錠剤などの医薬品の包装方法の1つです。凸型を形成した樹脂シートとアルミニウム箔でできており、薬の変質を防ぎ、材料によっていろんな機能を付与できます。そしてプラスチック部分を押すことで開口部のアルミ箔を破り、1錠ずつ取り出せます。
このPTPシートに包まれた医薬品を取り揃える業務は、薬剤師以外の人間が行っても問題ないとされています。その理由は、品質に影響がなく、薬剤師自身が最終確認できるからです。
2-2. 分包品のピッキング

薬局でのピッキングは、処方箋に記載されている医薬品を棚から必要な数だけ取り出す業務です。種類を正確に選ぶだけでなく、錠剤であれば錠数、外用薬ならば本数といった具合に、数量の正確性も重要です。
従来この業務を薬剤師以外が行うことは、グレーゾーンとされていました。しかし2019年4月の厚生労働省の通知によって、薬剤師以外の人間でも実施することが可能になりました。
今後の調剤事務員の役割は、受付や入力作業などの事務作業と、ピッキングや医薬品の棚入れや郵送などの調剤補助作業の2種類に分化していくことが予想されます。特にピッキングについては、オートメーション化が進んでいます。例えば、小型ロボットが薬剤トレイを入出庫します。またデータをレセプトコンピュータに入力すると、該当する薬剤トレイが自動搬送され、ロック解除したら入出庫口から薬剤を取り出せます。
2-3. 薬剤師以外の一包化薬剤の確認作業
薬剤師以外でも最終的な責任を負う薬剤師の指示に基づくという条件下で、できるようになりました。これは、薬剤師の監査の前に行う一包化した薬剤の数量確認業務です。この後の監査行為が前提になっているので、錠剤の一包化の可能性が高いといえます。
近年は、薬剤師が安心して他のスタッフに任せられる機器の開発が進んでいます。誰でも操作できる分包機が普及しつつあり、手間や安全性における薬局間の格差はなくなりつつあります。分包機については、『分包機とは?おススメの機種やコスト削減方法を解説します』で詳しく解説していますので、こちらも参考にして下さい。
3. これからの薬剤師に求められること
最近の調剤業務はIT化が進んでおり、薬剤師はより専門性とコミュニケーション能力を生かした分野での活躍が求められています。具体的には地域包括ケアシステムの一翼を担い、薬についていつでも気軽に相談できるかかりつけ薬剤師として役割が重視されています。そのポイントを、以下に記します。
3-1. 服薬情報の一元的・継続的な把握を実施する
主治医と連携し、聞き取りやお薬手帳の把握を通じて、患者さんがかかっている全ての医療機関と服用薬を一元的・継続的に把握します。例えば医療法人ONEきくち総合診療クリニック(神奈川県綾瀬市)の調査によると、65歳以上の7割の方が複数の病院を受診しています。それほど高齢者の患者さんは、複数の医療機関に通っている現状があります。また患者さんに複数のお薬手帳が発行されている場合、一冊化を行います。
3-2. 在宅対応・24時間対応の推進
日本は、総人口の4分の1以上が65歳以上という超高齢化社会を迎えています。高齢者の方には、複数の疾患を抱えている方もたくさんいます。そういった状況下では、薬局の開局時間外に薬の副作用や飲み間違いが発生します。そのための電話相談が求められています。
また夜間や休日においても、在宅の患者さんの症状が悪化した場合、調剤を実施する必要があります。現状として日本お薬局お半数以上は24時間対応が可能ですが、今後さらにそのシェアは高まるでしょう。
3-3. 他の医療機関との連携
例えば薬剤師が処方内容を医師に確認し、必要に応じて処方医に対して疑義照会や処方提案を行います。また調剤後も患者さんの健康状態を正確に把握し、処方医へフィードバックを行います。そして残薬管理や服薬指導を行います。
それ以外にも医薬品の相談や健康相談に対応し、他の医療機関の受診を勧奨する役割もあります。そのためには、患者さんの症状にはどの医療機関が適しているかといった情報の共有も求められます。
4. 薬剤師以外の一包化のまとめ
薬剤師以外の一包化やピッキングが、薬剤師の指示の元での実施という条件下で可能になりました。ただし、軟膏剤や水剤、散剤の混合などは薬剤師法違反になります。
高齢化社会化とDX化が進む中、薬剤師の働き方と薬局経営の在り方が大きく変わろうとしています。特に在宅医療については、DXの推進と薬剤師のコミュニケーションがその効果に影響を与えます。
国が推進する地域包括ケアシステムの中で、「薬局のあり方」「薬剤師のあり方」を模索する時代がしばらく続くでしょう。
本サイトではそういった最新事例についても、今後積極的に情報発信してく予定です。