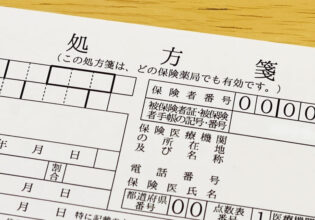薬剤師は、人の命を預かるやりがいのある仕事です。薬に関する専門知識を生かし、患者さんの健康を改善することに貢献できます。その象徴的なシーンは、「ありがとう」という患者さんの感謝の言葉です。この「患者さんを助けることができる」というやりがいは、多くの薬剤師の働くモチベーションになっています。
しかし一方で、薬剤師の仕事範囲は非常に広く、大変だと感じる方もいます。また調剤や服薬指導は人命に関わるため、ミスが許されません。その緊張感もストレスの原因になる可能性があります。
どんな仕事でも、モチベーションを維持することはとても重要です。常に学びながらスキルを磨き、お客さんに感謝されることが大切です。そのためには、自分に合うモチベーションを維持する方法が重要です。そこで本記事では、薬剤師のやりがいとは何か、またモチベーションを維持するにはどんな方法があるのかを解説します。
Contents
1. 薬剤師のやりがいとは
1-1. 患者さんの健康に貢献できる
薬剤師のやりがいといえば、やはり患者さんと触れ合い、その健康に貢献できることでしょう。例えば丁寧に症状をお聞きし、薬を調剤して使用することで、患者さんの病気を治します。
ここで重要なポイントは、病状に関して正確に把握し、患者さんにわかりやすく伝えることです。また患者さんの話を丁寧に聞いて、正しく服用できるようにアドバイスします。患者さんの病気を治すためには、このコミュニケーションがとても大事です。この信頼関係の結果、病気が完治し、「ありがとう」と感謝の言葉をもらえることが、大きなヤリガイになります。「処方薬の効果があり、患者さんの笑顔が見られた時」は、薬剤師という仕事の醍醐味といえます。
1-2. 薬の専門知識を生かして医療貢献できる
薬剤師は、”薬のスペシャリスト”です。薬の専門家として、医療に貢献できるのも薬剤師の大きなやりがいです。
例えば医療用の医薬品の数は、約1万7千種類もあります。しかも、薬局には日々様々な診療科目の処方箋が持ち込まれます。そういった局面において、薬に関する豊富な知識を生かすことができます。
また調剤薬局や病院だけでなく、製薬メーカーや食品会社の研究職やMR(医療情報提供者)としても活躍できます。それだけでなく、医薬品製造施設での管理薬剤師業務や行政機関や医薬教育の現場など、幅広い分野で薬の専門性が活かされます。近年は、がん専門薬剤師や糖尿病薬物療法認定薬剤師など、より高度な知識をもつ薬剤師も増加しています。
1-3. ライフステージに合わせた働き方ができる

薬剤師は、難易度の高い国家資格です。そのため一度取得できれば、ご自身のライフステージに合わせた働き方ができるのも、薬剤師ならではのやりがいです。
例えば、女性の薬剤師が結婚・出産で働き方を変える必要が発生した場合です。その状況に合わせて時短勤務にすることで、仕事と子育てを両立することができます。また子育てが落ち着いたら、フルタイムに復帰するもできます。
しかも地方の薬局や病院などでは、深刻な薬剤師の採用難に悩まされているところも少なくありません。その大きな理由は、都市圏への流出による人材不足です。そのため、薬剤師が少ない地域では年収が上がりやすい傾向があります。
2. 働く場所でも変わる薬剤師のやりがい
薬剤師の働く場所は、多岐に渡ります。それぞれ異なった魅力ややりがいがあるので、ここではそれらについて解説します。
2-1. 薬局
薬局の薬剤師のやりがいは、患者さん一人一人を継続的にケアできることです。まさに患者さんの”健康のコンシェルジェ”として、寄り添いながらサポートできる重要な機能を果たしています。
2016年4月、「かかりつけ薬局・薬剤師」制度が導入されました。また同年10月1日には「健康サポート薬局」の届け出がスタートしました。この背景には、医薬分業のメリットを活かし、患者さんの健康を守るニーズがあります。
今後は、患者さんの「1つの薬局・1人の薬剤師化」がより推進されていくでしょう。つまり患者さんにとって、自分の服薬情報を全て一元的に管理している専用の薬剤師になっていきます。そうすることで、より献身的で精度の高いサポートを実現することができるようになります。
2-2. 病院
病院で働く薬剤師のやりがいは、先端医療に関われることと、チーム医療に代表される多職種との連携です。例えば治験業務では、新薬の研究や予防法の研究を行います。こういった業務は、病院で働く薬剤師ならではでしょう。
チーム医療では、医師や看護師、作業療法士や理学療法士など様々な職種が連携します。そうした中で、医師に処方の根拠を直接聞けたり、薬のサポートでリハビリ専門職と関わったりするのも大きなやりがいです。
また調剤業務では、処方鑑査や疑義照会などを行います。例えば調剤終了後に与薬カートのセットを行い、病棟まで処方薬を届ける業務は病院薬剤師ならではといえます。
2-3. 医薬品関係企業
製薬メーカーに代表される医薬品関係企業は、公益以外にビジネスとしてもやりがいがあります。また年収が高いことでも知られており、薬局勤務からの転職者が多いのも特徴です。
具体的な職種としては、「管理薬剤師」「MR」「CRC」「品質管理・品質保証」「研究開発」などがあります。例えば管理薬剤師の場合、主に医薬品の管理を行います。本社勤務の場合、薬の在庫管理やDI業務、医師からの問い合わせ対応があります。また工場勤務の場合の多くは、医薬品製造における品質管理を担当します。
治験コーディネターの場合、被験者へのインフォームドコンセントやスケジュール管理、服薬指導、データや資料の作成を行います。このように、医薬品関係企業での薬剤師のやりがいは、ビジネスの醍醐味と収入の高さが大きな特徴です。
3. 仕事のモチベーションを保つ方法
3-1. 先輩に相談する

困ったことや相談ごとがある時、先輩に相談することで解決できることが結構あります。特に業務でわからないことが発生した場合、自分よりも知識も経験もある先輩は心強い存在です。スピーディに解決に導いてくれるでしょう。
「ほうれんそう(報告・連絡・相談)」といわれるように、業務を円滑に進める上でこの3つは非常に大切です。またそういったコミュニケーションは、円滑な人間関係につながる効果があります。自分が働きやすい職場環境作りという視点でも、先輩への相談は効果的な解決策といえます。
3-2. 自分の目標を設定する
目標設定による自己成長は、薬剤師としての職務にやりがいを持たせる上でとても重要です。また設定した目標を達成することで得られる自信は、モチベーションの安定やストレス管理につながります。
例えば定期的なセミナーや勉強会への参加は、自分スキルの向上を実現できます。また新薬情報のアップデートは、患者さんへのアドバイスの精度の向上につながります。目標達成を目指して新しいことを学ぶと、楽しさや自分の成長を実感できます。その結果、日常の仕事に対するモチベーションが高まり、仕事のやりがいを感じることにつながります。
3-3. リフレッシュする
薬剤師の仕事は、体が資本です。疲れて集中力が落ちてくると、ヒヤリ・ハットや調剤過誤を起こす原因にもなります。例えば一人薬剤師の薬局の場合、どうしてもそういった状況になりやすい傾向があります。
そういった状況になった場合、有給休暇を取得しましょう。今までいったことのない場所に訪れれば、リフレッシュ効果も期待できます。また近年は、マインドフルネス(瞑想)も人気です。道具要らずで簡単に実践でき、ストレスや不安、高血圧や不眠症などに効果があるといわれています。
4. まとめ
薬剤師は、薬物療法を通じて、患者さんの症状改善に貢献できる重要な仕事です。常にその専門性を自己研鑽し、患者さんから感謝されるヤリガイがあります。
薬剤師の約6割を占める薬局においては、今後は更に対人業務が占める割合が高まることが予想されます。そうした環境の中でモチベーションを維持しながらヤリガイを感じるためには、対人コミュニケーションスキルが必要不可欠です。
薬に関する専門知識だけでなく、様々な疾患をお持ちの患者さんへの対応能力がより重要になってくるでしょう。例えば本サイトでは、服薬指導における会話例を掲載しています。こちらの『服薬指導の会話例とは?患者さんに分かりやすく伝える実例を解説』もぜひ参考にしてください。